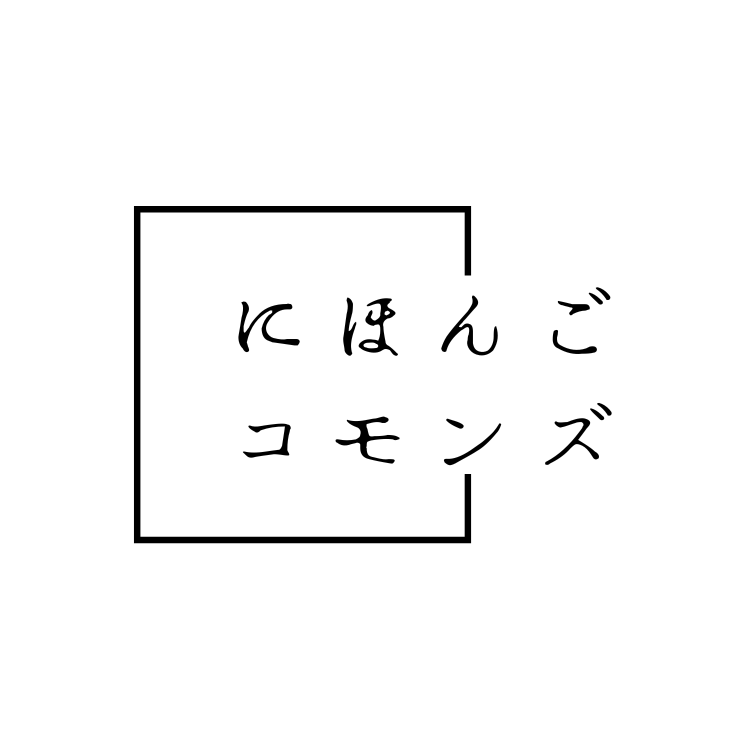地域日本語教育を「ないもの探し」から「あるもの探し」へ──『「みんな」って誰?』を読んで考えたこと
地域日本語教育の現場では、支援者不足や予算不足など、「ないもの」に焦点が当てられることが多くあります。もちろん、それらは無視できない大切な課題です。けれども、人口減少や財政難が進むなか、単純に人やお金を増やすことは、現実的には難しくなっています。
そんなときに出会ったのが、宮本匠さんの『「みんな」って誰?──災間と過疎をのびのび生きる』(世界思想社)です。本書は、著者が中越沖地震の復興支援に携わった経験をもとに、災害で無力感が漂っていた地域が、少しずつ「空気」を変えていく過程を描き出しています。「みんな(=空気)」という見えにくい存在が、どのようにして地域や組織に影響を与えるのか、その働きを丁寧にひもといていきます。
私自身、本書を通して多くの気づきを得ましたが、特に印象に残った点を地域日本語教育に引き寄せて書いてみたいと思います。
まず強く心に残ったのが、「ないもの」ではなく「あるもの」に目を向けるという視点です。本書では、「ないもの探し」は無力感を強めるものであり、「あるものさがし」への転換が大切だと説かれています。私は地域日本語教育コーディネーターとして、日本語教室で活動する皆さんによく課題を聞いていました。多くの教室から「支援者が足りない」「予算がない」といった声を聞きますが、改善される気配はなかなか見えません。けれども本書を読み、今そこにある小さな資源や日々の活動を支えている人たちの存在にもっと目を向けることで、希望の芽につながるのではないかと考え直しました。
皆さんのまわりには、どんなものが「あります」か?
もうひとつ印象的だったのが、支援者が「受容的に関わる」という姿勢です。
本書では、復興支援に関わった大学生たちが地元の人々に教えを乞うように接し、相手の中にある力や想いを引き出していく様子が描かれていました。私はこれまで、支援とは「能動的に何かしてあげること」だと思い込んでいました。強い想いや行動力がないと続けられない、と。しかし、そうではなく、相手の持つ力に耳を傾けることもまた立派な支援であり、この姿勢は地域日本語教育においても大切にしていきたいと感じました。
本書を通じて学んだのは、どんな状況の中にも、静かに起こりうる変化がたしかに存在するということです。
ないものを嘆くのではなく、あるものを信じ、そこから歩き出す。そんな視点を、これからの地域日本語教育に少しずつ根づかせていきたい。まずは、自分から始めてみます。
紹介した本はこちら:
宮本匠『「みんな」って誰?──災間と過疎をのびのび生きる』(世界思想社)
出版社サイトで内容を読む
※この記事は、読書メモとして本書を読み、自身の実践と照らし合わせた内容です。