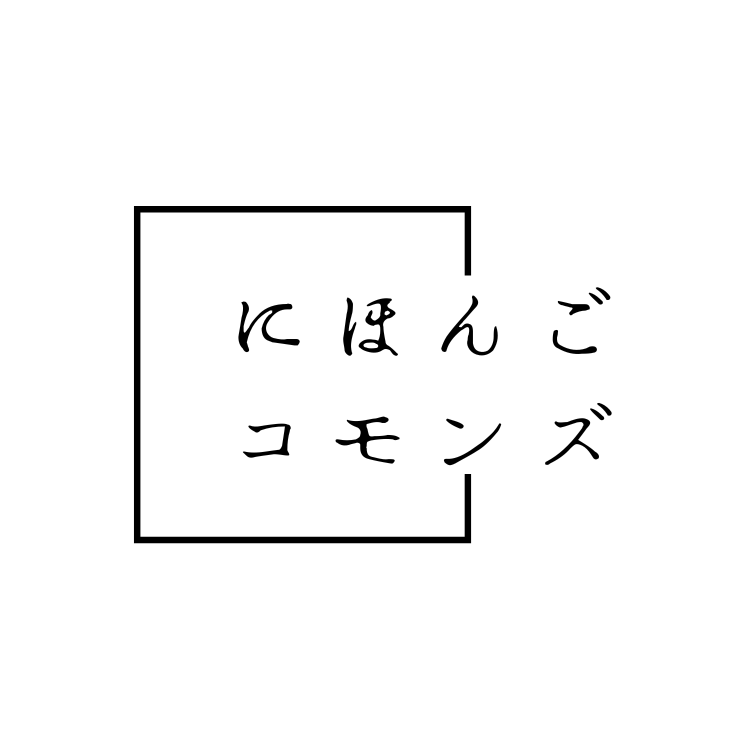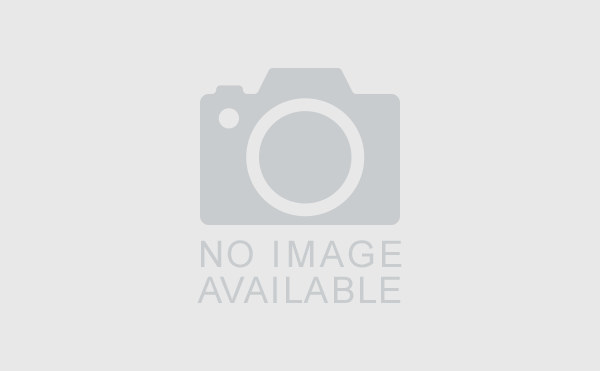「やさしい日本語」に大切な3つの視点
「やさしい日本語」と聞くと、「言葉を簡単にすること」だと思われるかもしれません。もちろんそれも大切です。しかし、根底にあるマインドや姿勢も見落としてはいけません。今回はやさしい日本語に大切な視点を3つご紹介します。
視点1:背景を知る
やさしい日本語を使うとき、まず意識したいのは相手の背景です。外国人住民と一口に言っても、出身国、母語、日本での滞在歴、来日の目的、生活環境はさまざまです。たとえば、母語に漢字があるかないか、日本語の学習経験がどの程度あるかによって、理解できる言葉は違ってきます。
また、専門分野の日本語は理解できる方が、それ以外の生活場面では日本語に戸惑うこともあります。たとえば、工場で長年働いている方で、仕事に関する日本語(機械操作や工程管理など)には強い方も、役所の手続きや学校からの連絡のような場面ではわからない言葉に直面する、などです。そのほか、日本人配偶者がいる外国人の方の場合、家族や友人との会話には困らないほどの日本語力を持っていても、役所や病院などで使われる日本語(専門用語、敬語など)には不慣れで、理解しにくいこともあります。
「どこが得意で、どこが難しいのか」は人それぞれ違います。単に「日本語ができる・できない」で判断しないようにしましょう。相手の背景や状況に応じて寄り添うことが、本当の意味でのやさしさにつながります。
視点2:相互理解を育む
やさしい日本語を使うとき、もうひとつ大切なのが相互理解を育む姿勢です。たとえば、説明した後に「ここまででわからないことはありますか?」「なんでも聞いてくださいね」など声をかけてみてください。そうすれば、相手も安心して質問できる雰囲気が生まれます。また、相手の反応をよく観察し、表情やしぐさから「伝わっているかどうか」を感じ取ることも重要です。戸惑っている様子があれば、別の表現を試してみる柔軟さが求められます。
ここで注意したいのは、相手を子ども扱いしないことです。日本語が苦手なだけで、相手は大人です。豊かな知識や経験を持ったひとりの人格者です。ところが、時折、日本語が拙いからといって、子どもに接するような態度をとってしまう日本人を見かけます。
-必要以上に声を大きくする
-あからさまに簡単すぎる言葉で話しかける
-「よくできたね」といった子どもに向けるような言葉をかける
これらは、知らず知らずのうちに相手を傷つけてしまうことがあります。言葉をやさしくしても、態度や心構えが上から目線にならないよう、細やかな配慮が求められます。
視点3:環境を整える
環境を整えることも重要なポイントです。たとえ言葉をやさしくしても、その情報が相手に届かなければ意味がありません。
たとえば、以下のような状況では、日本語が苦手な方は情報のアクセスが難しくなります。
-市役所の窓口にやさしい日本語で書かれた案内がない
-学校からのお便りが難しい言葉で書かれている
-地域イベントのチラシが日本語のみで作られている
やさしい日本語を生かすためには、伝達手段そのものを工夫することも求められます。
現在は「多言語表記を併用する」「相談できる窓口を整備する」などの取組が進められています。
おわりに
やさしい日本語は、単なる「言葉の言い換え」ではありません。背景を知り、相互理解を育み、環境を整える。大切なのは、相手を尊重するマインドと誠実に伝え合おうとする姿勢です。
✏️具体的な工夫を知りたい方へ(資料紹介)
今回ご紹介した3つの視点は、やさしい日本語の心構えに関するものです。実際にやさしい日本語を使うときの工夫については、こちらの資料もご覧ください。マインドと技術の両方を意識することで、やさしい日本語はさらに力を発揮します。