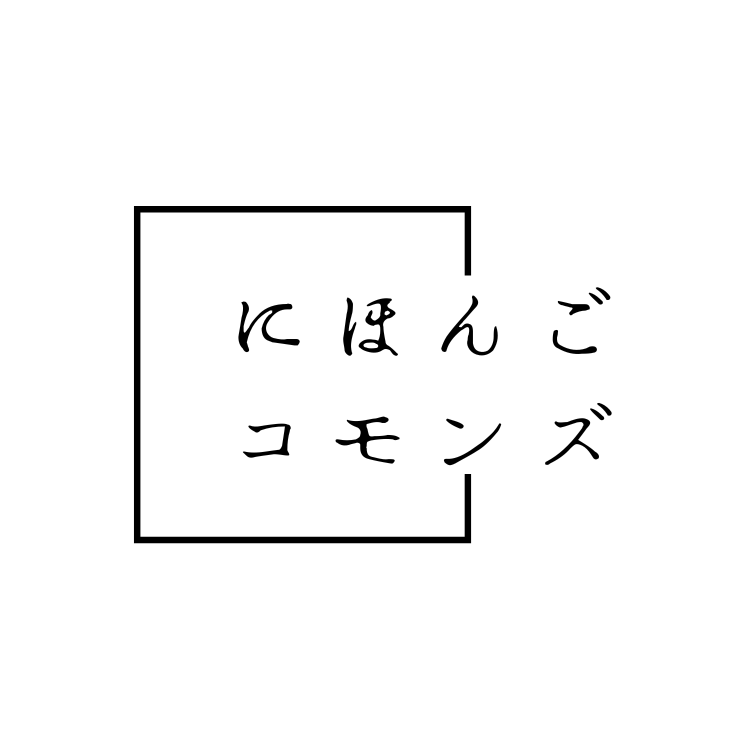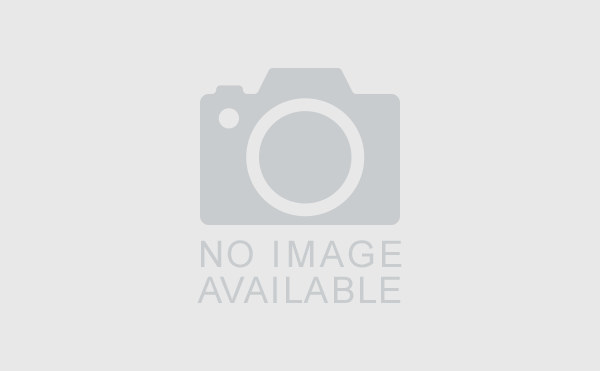地域日本語教育コーディネーターの課題とは?②孤立
コーディネーターとは、人と人、人と制度、人と地域をつなぐ仕事です。多様な立場の人たちの間に入り、理解を促し、利害を調整しながら一つの方向へ導いていく。調整役として不可欠な存在でありながら、皮肉なことに、その役割ゆえに「孤立」しやすい職種でもあります。
「相談される側」の孤独
地域日本語教育コーディネーターを例にとれば、支援者、行政、地域住民、外国人住民など、さまざまな人々から頼られる存在です。「こんな場合はどうすればいいですか?」「支援がうまくいかないのですが…」と日々多くの相談が寄せられる一方で、自分自身が悩みを相談する場は意外なほど少ないのが現実です。
「相談される側」だからこそ、声を上げにくく、自分の孤立に気づきにくいという paradox(逆説)があるのです。
孤立の背景:専門性の交差点に立つ難しさ
コーディネーターの仕事は、単独の専門領域に収まりません。地域日本語教育なら日本語教育、地域福祉、行政制度といった複数の専門性をまたぎます。しかし、だからこそ、自分の専門分野のコミュニティに帰属しにくいという課題があります。教育職でなければ、福祉職でもない。行政職でもない。その「間」に立つことが、専門的な学びや共感的な支えを得にくくしているのです。
経験共有の不足と、燃え尽きリスク
さらに大きいのが、経験共有の機会不足です。現場での試行錯誤は非常に貴重な学びになりますが、個々の中に留まりがちです。困ったときに「同じ立場の仲間に話せる」環境がないと、課題を抱え込んでしまい、燃え尽き症候群(バーンアウト)に至るリスクも高まります。とりわけコーディネーターは、自分自身が支援者として存在するため、無意識のうちに「まずは他者優先」に陥りがちです。自分自身のケアを後回しにしてしまうことが、孤立感をさらに深めます。
孤立を防ぐ「つながり」の設計を
では、この孤立をどう防ぐことができるのでしょうか。
鍵は「意図的なつながりの設計」です。たとえば、文部科学省では地域日本語教育コーディネーターを対象に「地域日本語教育コーディネーター研修」が行われており、ネットワークや学びの場をつくる動きが生まれています。コーディネーターは、「つなぐ」ことを生業としながら、つなぐ先が自身には届きにくいという矛盾を抱えています。だからこそ、自分たち自身がつながり合える場を大切に育てていく必要があります。
「孤立するコーディネーター」を生まないこと。
それは、ひいては支援される人々の孤立を防ぐことにもつながっていきます。