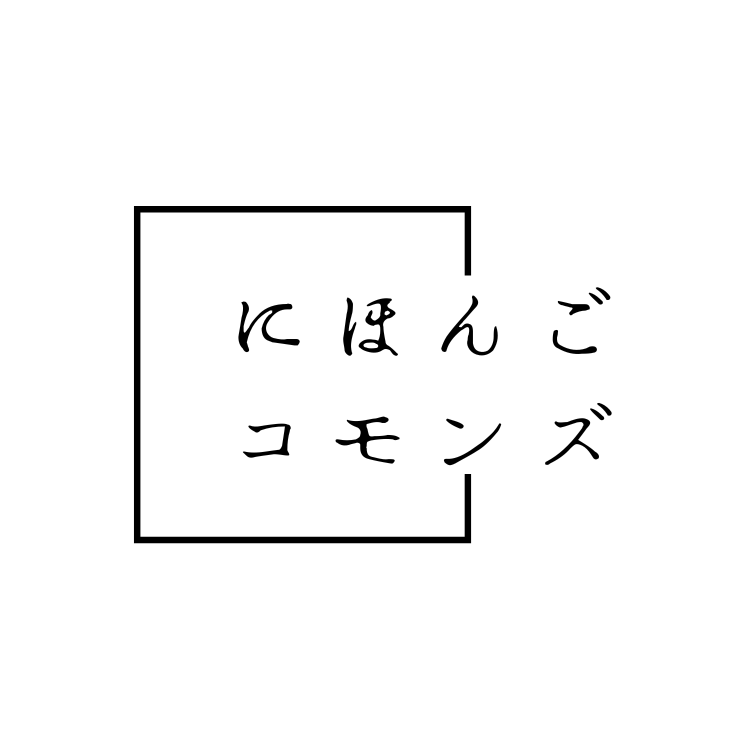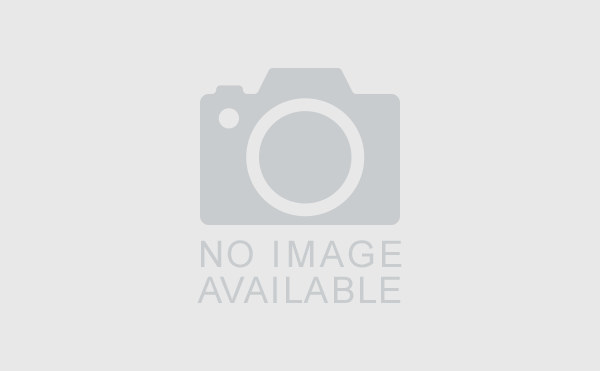地域日本語教育コーディネーターの課題とは?①養成
コーディネーター職の重要性が高まる一方で、その養成には大きな課題が横たわっています。それは、「経験に依存しがちなスキルセットを、いかに体系的に育成するか」という問題です。
1. 「場数」でしか得られない実践知の壁
多くのコーディネーターが語るのは、「やってみないとわからない」という現実です。たとえば地域日本語教育コーディネーターとして、地域の多様な立場の人々と関わる中で、初めて支援者の葛藤や学習者の声にならない悩みに気づくことができます。こうした「暗黙知」ともいえる実践知は、標準化やマニュアル化が難しい。だからこそ、養成段階でいかに「疑似体験」や「ケーススタディ」を重ね、現場感覚に近づけるかが大きな課題です。
2. 専門性の多層性と、学際的アプローチの必要性
コーディネーター職は単一の専門性だけでは成り立ちません。地域日本語教育なら、日本語教育の知識だけでなく、多文化共生論、地域福祉、行政制度への理解が不可欠です。学際的な学びの場の設計が求められます。
3. 「調整力」の見える化と評価の困難さ
コーディネーターに欠かせない「調整力」は、成果が数字で表れにくい能力です。たとえば地域の外国人住民と支援者の関係がスムーズになったとき、その裏にはコーディネーターの丁寧な根回しや対話の積み重ねがありますが、これを評価指標として表すのは非常に難しい。養成の場でも「何ができれば一人前なのか」という基準づくりが不十分で、属人的な評価に頼らざるを得ない状況があります。今後は、調整過程のプロセス評価や、当事者の満足度などを組み合わせた多面的な評価方法が必要です。
4. 持続的な学びの機会とコミュニティ形成の不足
コーディネーターは、現場で孤立しやすい職種でもあります。地域日本語教育コーディネーターは特にそうですが、地域の小さな単位で活動することが多く、専門家同士がつながる機会が限られています。これが、スキルのブラッシュアップやメンタルヘルスの観点でも課題となります。養成だけで終わらず、実践に入った後も継続的に学び合える「コーディネーター・コミュニティ」の育成が急務です。相互支援や知見の共有によって、現場での課題解決力は格段に高まるでしょう。
まとめ
コーディネーター養成の課題は、単なるスキル習得にとどまりません。多様な専門性を束ねる「専門職」としての自覚と環境づくりが不可欠です。そのためには、経験に依存しすぎない体系的な育成と、現場の孤立を防ぐ学びのコミュニティづくりが両輪となります。