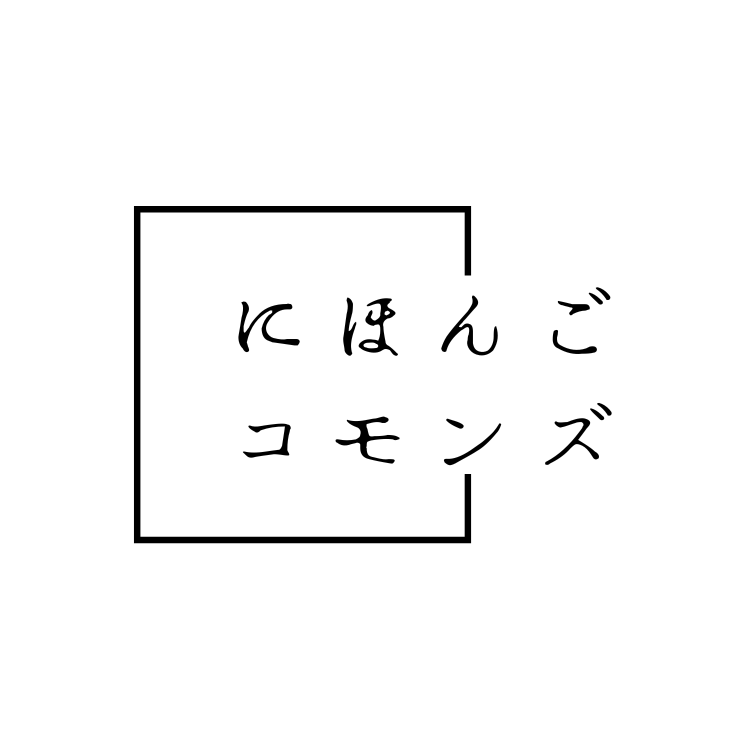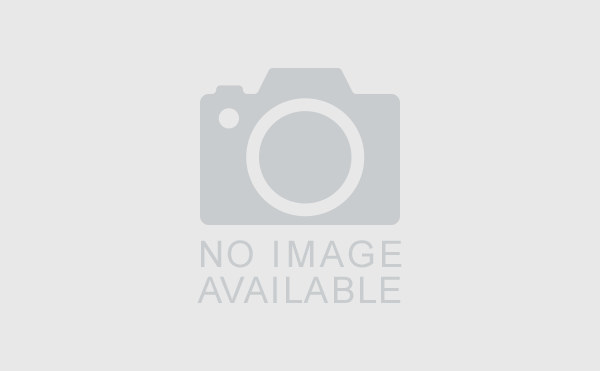「コーディネーター」の仕事に共通するもの 〜地域日本語教育コーディネーターから考える〜
「コーディネーター」と名のつく職業は、実は私たちの生活のあらゆる場面で活躍しています。たとえば、私が関わっている「地域日本語教育コーディネーター」。そのほかにも「移植コーディネーター」「観光コーディネーター」「子育て支援コーディネーター」など、分野も規模もさまざまです。しかし、その名前のとおり「コーディネート(調整・つなぐ)」するという役割には共通点があります。
地域日本語教育コーディネーターは、地域で日本語を学びたい外国人住民と、学びを支えるボランティアや日本語教師、行政機関、企業、そして地域社会そのものをつなぐ役割を担います。学びの場をつくるだけでなく、外国人住民が地域で孤立しないようサポートし、多文化共生のまちづくりを支える調整役です。
移植コーディネーターの場合も、ドナーとなる方の意思を尊重しつつ、移植が必要な患者、医療チーム、家族、関連機関との調整を行います。
観光コーディネーターは、地域の魅力を引き出し、観光客、地元事業者、行政、地域住民といった多様な主体をつなぎます。単なる観光案内ではなく、地域資源をどう活用するか、持続可能な観光の仕組みづくりまで関わるケースもあります。外から人を呼び込むだけでなく、地域の誇りや経済を支える存在です。
子育て支援コーディネーターもまた、地域の子育て家庭と、行政サービスや地域のサポート資源をつなぐ役目です。育児の孤立を防ぎ、親同士のつながりを促したり、必要な支援にたどりつけるように伴走します。
これらに共通するのは、「多様な主体をつなぐ橋渡し役」という点です。それぞれの立場や背景、価値観を理解しながら、お互いが無理なく関われるように調整し、全体を前に進める。コーディネーターは目立つ立場ではないかもしれませんが、その存在がなければ、関係者の間に溝が生まれたり、支援が届かなかったりすることもあるでしょう。
さらに、どのコーディネーターにも共通する「柔軟さ」と「専門性」の両立が求められていることが見えてきます。たとえば地域日本語教育コーディネーターなら、日本語教育の知識はもちろん、多文化共生や地域づくりの視点が必要です。移植コーディネーターも、医療の専門知識に加え、人としての誠実さや、状況に応じた判断力が重要です。観光コーディネーターなら、地域資源に関する知識と、観光業のトレンドやマーケティングの感覚も欠かせません。
そして、何より、「当事者の声を聴き取る力」がすべてのコーディネーターに共通する重要な資質です。地域の外国人住民、移植が必要な患者、観光客、育児中の保護者など、さまざまな立場の声に耳を傾け、その声をもとに必要な人や資源を結びつけていく。ここに、コーディネーターとしての醍醐味と責任があるのだと思います。分野は違っても、コーディネーターは「つなぐ」「調整する」「前に進める」存在。だからこそ、どの現場でも必要とされ、社会にとって欠かせない役割を果たしています。