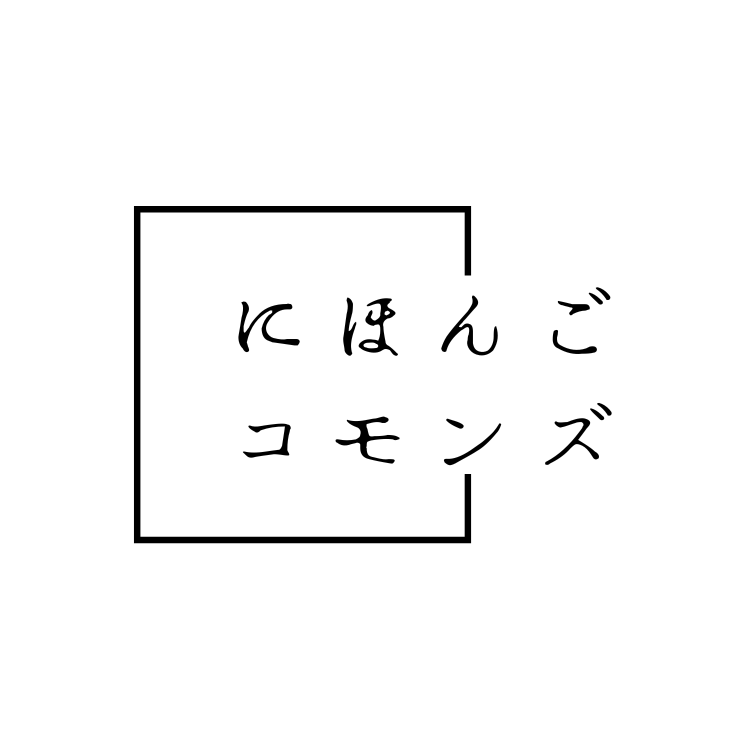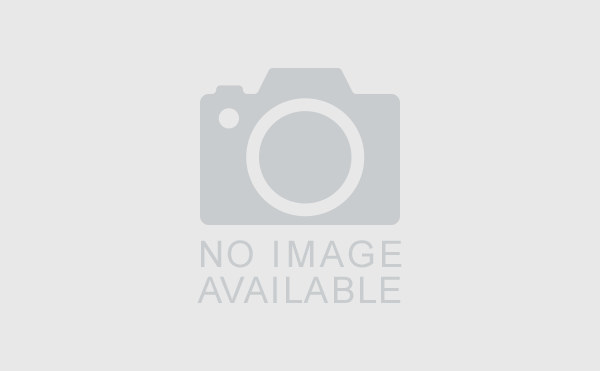やさしい日本語って?
誕生の経緯
みなさん、「やさしい日本語」という言葉を聞いたことがありますか。やさしい日本語は、1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに考案されました。当時、外国人向けの情報提供は英語が中心でしたが、日本語も英語も理解できず、重要な情報を受け取れない人が多くいました。そこで、日本語を簡単にして伝える方法が求められるようになりました。現在では、災害時だけでなく、役所の窓口、病院、学校、企業など、さまざまな場面で活用されています。
「やさしい日本語」のポイント
やさしい日本語には、いくつかのポイントがあります。
① 一文を短くする
日本語は、一つの文が長くなりやすい言語です。しかし、長い文は理解しづらくなります。
そこで、できるだけ 一文を短く しましょう。
例:
❌「窓口で申請書を記入した後、受付に提出し、証明書を受け取ってください。」
✅「窓口で申請書を書きます。次に、受付に出します。そして、証明書をもらいます。」
② ゆっくり、はっきり話す
外国人にとって、日本語の「速さ」は理解の大きな壁になります。
「ゆっくり」「はっきり」話すこと を意識すると、相手に伝わりやすくなります。
③ 難しい言葉をやさしく言い換える
漢語、敬語、控えめな表現などはできるだけ避けましょう。
もし使わなければならないときは、簡単な言葉で 言い換え ましょう。
| 難しい言葉 | やさしい日本語 |
|---|---|
| 記入する | 書く |
| 提出する | 出す |
| ご記入ください | 書いてください |
| 写真はご遠慮ください | 写真は撮らないでください |
また、「二重否定」も分かりにくい表現のひとつです。
⑤ 漢字を減らし、ひらがな・カタカナを活用する
日本語での会話が問題なくできる方でも、漢字の読み書きが苦手な方は多くいます。漢字の量には注意してください。
漢字を使うときは、漢字にルビを振るなどの対応をするといいでしょう。
⑥ ジェスチャーやイラストを使う
言葉だけで伝えようとすると、どうしても難しくなります。ジェスチャーやイラスト、写真を使うと、さらに分かりやすくなります。
やさしい日本語を使うメリット
やさしい日本語は、外国人だけでなく、日本人にとっても分かりやすい表現です。特に、小さな子どもや高齢者に有効だと言われています。言葉の壁をなくし、お互いに理解し合える社会をつくるために、ぜひ日常生活で「やさしい日本語」を意識してみてください。