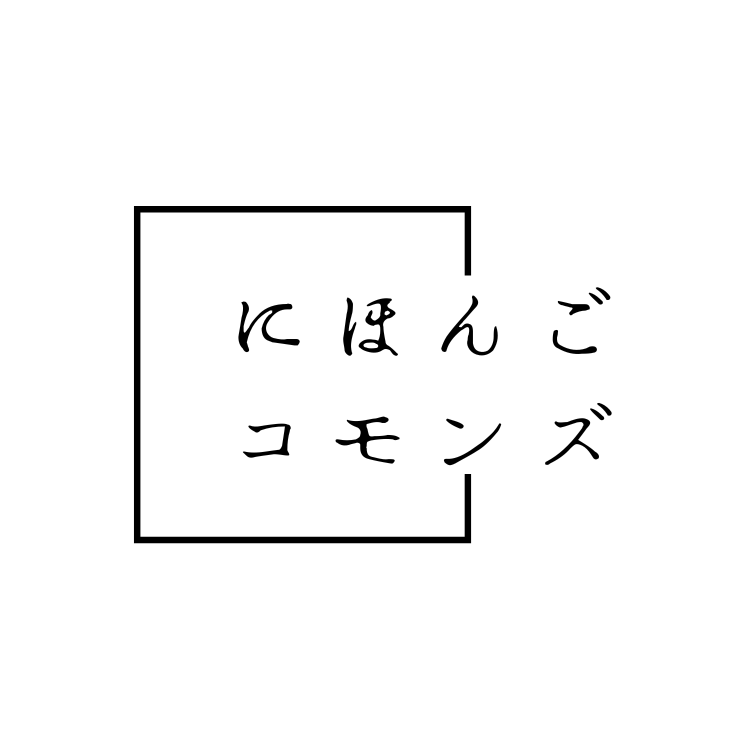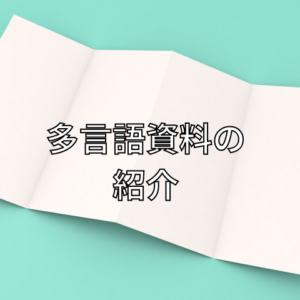ワークショップデザイナープログラムを振り返って
ふだん、私は「やさしい日本語」や「地域日本語教育」に関わる仕事をしています。仕事の一環で研修を行うことがあり、その中で自分なりにワークショップを取り入れていたのですが、どこかいつもモヤモヤしていました。「これで合ってるのかな…」「ちゃんと伝わってるのかな…」そんな不安が拭えなかったんです
きちんと学んでみたい。土台から組み立て直してみたい。そんなことを考えていたときに出会ったのが、青山学院大学の「ワークショップデザイナープログラム」です。今回は、ちょっといつものテーマからは外れますが、この研修を通して感じたことを振り返ってみようと思います
同じようにワークショップや研修に悩んでいる人にも、少しでも参考になればうれしいです。
自分のワークショップに“背骨”ができた
研修を通して、自分の中にしっかりと「背骨」が通ったように思います。これまでは感覚でやっていたことに、理論や視点が加わったことで、「こういうふうに考えればいいんだな」という道筋が見えるようになりました。
「コンセプトメイキング」「参加の保証」「参加の増幅」「身体性/即興性/協働性」…
他にもたくさんのことを学び、今でもワークを考えるときの大事なヒントになっています。
振り返り(リフレクション)も、以前は「何か気づいたことありますか?」とざっくり聞いて終わりでしたが、今は“型”や意図を意識して、少しずつ深めていけるようになってきました。
今の仕事にもちゃんと活きている
そして、今、その学びは日々の仕事に生きています。研修の講師として仕事を請けるとき、このプログラムで学んだことが自然と頭に浮かんできます。
「この研修、なんのためにやるんだろう?」
「足りてない要素は?」
「参加者が“自分ゴト”として受け取るにはどうすれば?」
そんなふうに問いかけながら、全体の構成を考えたり、進行を調整したりしています。
前よりもずっと、自信を持って“場”をつくれるようになったと感じています。
これからも一緒に育ち合える場をつくりたい
このプログラムを通して、「もっといろんなワークショップに挑戦したい」と思うようになりました。今までは“決まった型”に頼ることが多かったけれど、学びを踏まえていれば、もっと自由に、のびのびとやれる気がしています。
自分自身も楽しめること。そして、なにかを“教える”というより、「気づき」が生まれるような場にすること。参加者と一緒に考えたり、驚いたり、笑ったり。そんな場をこれからもつくっていけたらいいなと思っています。