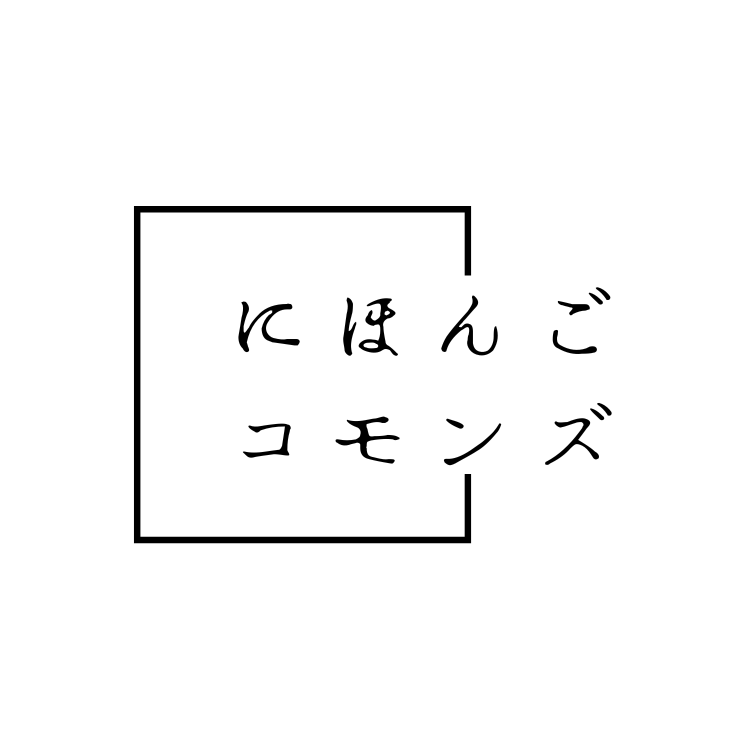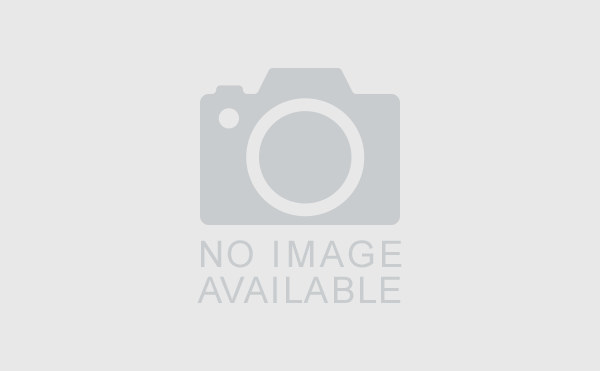ユニバーサルデザインの視点から「やさしい日本語」資料を見直してみた
〜小さな工夫が、みんなの「わかる」をつくる〜
「やさしい日本語」の資料をつくるとき、私はいつも“誰にとっても見やすく・伝わりやすい”を意識しています。でも、あるとき友人から「色弱の人にとっては、色の使い方が少し気になるかも」とアドバイスをもらいました。
そこで今回、先日公開した資料のデザインを少し見直してみました。比べてみると、違いがいくつか見えてきます。
↓旧バージョン

↓新バージョン

🍀 工夫1:タイトルの文字を囲って、背景との差をはっきりと
旧デザインでは、背景色と文字色がやや近く、文字が埋もれて見える可能性がありました。
新しいデザインでは、タイトル部分を囲ってコントラストを高め、パッと目に入りやすくしました。
🍀 工夫2:色ではなく「吹き出し」で強調
目立たせたい部分を“色で区別する”のはよくある方法ですが、色覚に差がある人にとってはその差が伝わりにくいことも。そこで今回は、吹き出しを使ってポイントを明示するように変更しました。
この工夫は、色弱の方だけでなく、多くの人にとって「わかりやすい」につながると思います。
まさに「やさしい日本語」と同じ。伝える相手に寄り添って、少しの工夫を重ねること。
それが「誰かの安心」につながるのだと実感しています。
皆さんもぜひ、ユニバーサルデザインの視点から、ふだん使っている資料を見直してみてはいかがでしょうか?