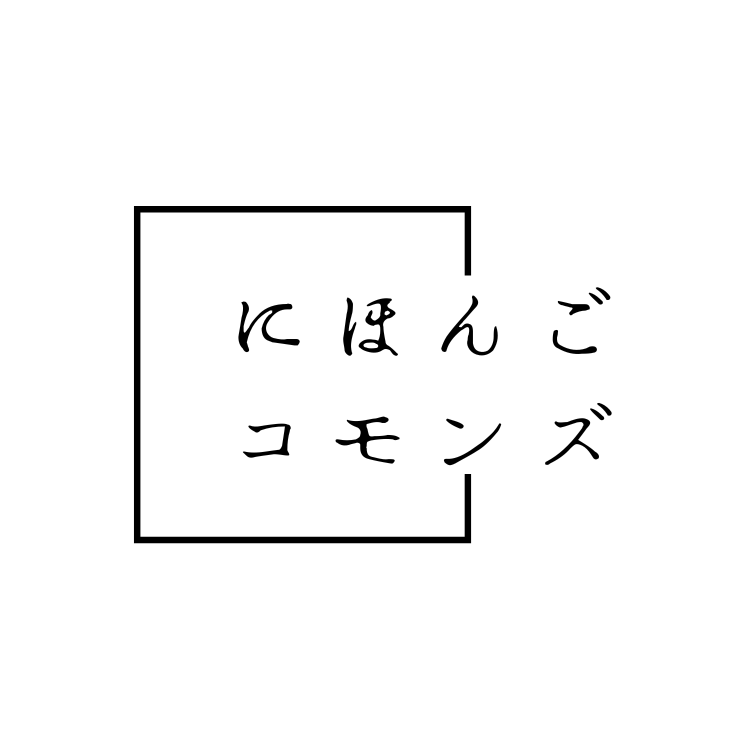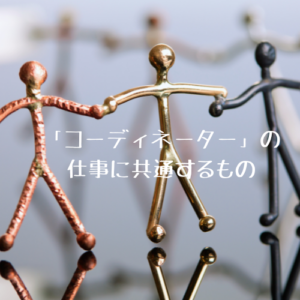災害時に役立つ「やさしい日本語」
地震や台風など、自然災害が多い日本。
そのとき、私たちは「命を守る行動」をすばやく取らなくてはいけません。
でも、情報をキャッチするのは簡単ではありません。とくに日本語が苦手な方や、聞き慣れない言葉にふれる外国人住民にとって、災害時の「難しい言葉」は大きな壁になります。「やさしい日本語」を使った防災・減災の取り組みが注目されています。
伝わらないと、行動できない。
たとえば、こんな表現を聞いたことはないでしょうか?
- 「避難指示が発令されました」
- 「土砂災害の危険が高まっています」
- 「警戒レベル4:全員避難」
日本語に慣れている私たちでも、いざというとき意味を取り違えてしまいそうです。
外国人住民や、難しい言葉が苦手な方にとっては、そもそも意味がわからないまま時間だけが過ぎてしまうかもしれません。
「避難指示」とは何をすればいいのか?
「発令」ってどういうこと?
「警戒レベル4」ってどのくらい危ないの?
命に関わる情報だからこそ、迷わず行動できるように伝える工夫が必要です。
やさしい日本語で「すぐにわかる」情報発信を
難しい言葉も、少し言いかえるだけでわかりやすくなります。
| 元の表現 | やさしい日本語 |
|---|---|
| 避難指示が発令されました | 危ないです。安全な場所へにげてください。 |
| 土砂災害の危険が高まっています | 山や川がくずれるかもしれません。にげるじゅんびをしてください。 |
| 警戒レベル4:全員避難 | とてもあぶないです。にげてください。 |
ポイントは「短く」「わかりやすく」。
専門用語は使わず、できるだけ具体的に「何をすればいいか」を伝えることです。
さらに、絵や図を使ったり、色を分けたりすることで、情報がよりスムーズに伝わります。
一人ひとりができること
防災は、情報の受け手だけでなく、伝える側にも工夫が必要です。
もしあなたが地域の防災リーダーだったら?
もしあなたが外国人の友だちに避難を呼びかける場面があったら?
「やさしい日本語」で伝えることができれば、きっと相手の安心につながります。
- むずかしい言葉をやさしく言いかえる
- ゆっくり、はっきり伝える
- ジェスチャーや地図も使う
ほんの少しの工夫で、守れる命があります。
おわりに
「やさしい日本語」は、非常時だけの特別なものではありません。日ごろからやさしい言葉でコミュニケーションを心がけることで、
災害時にも自然と役立つ力になります。誰もが安心して暮らせる街をつくるために、まずは「やさしい日本語」で、いざというときの備えを
始めてみませんか?